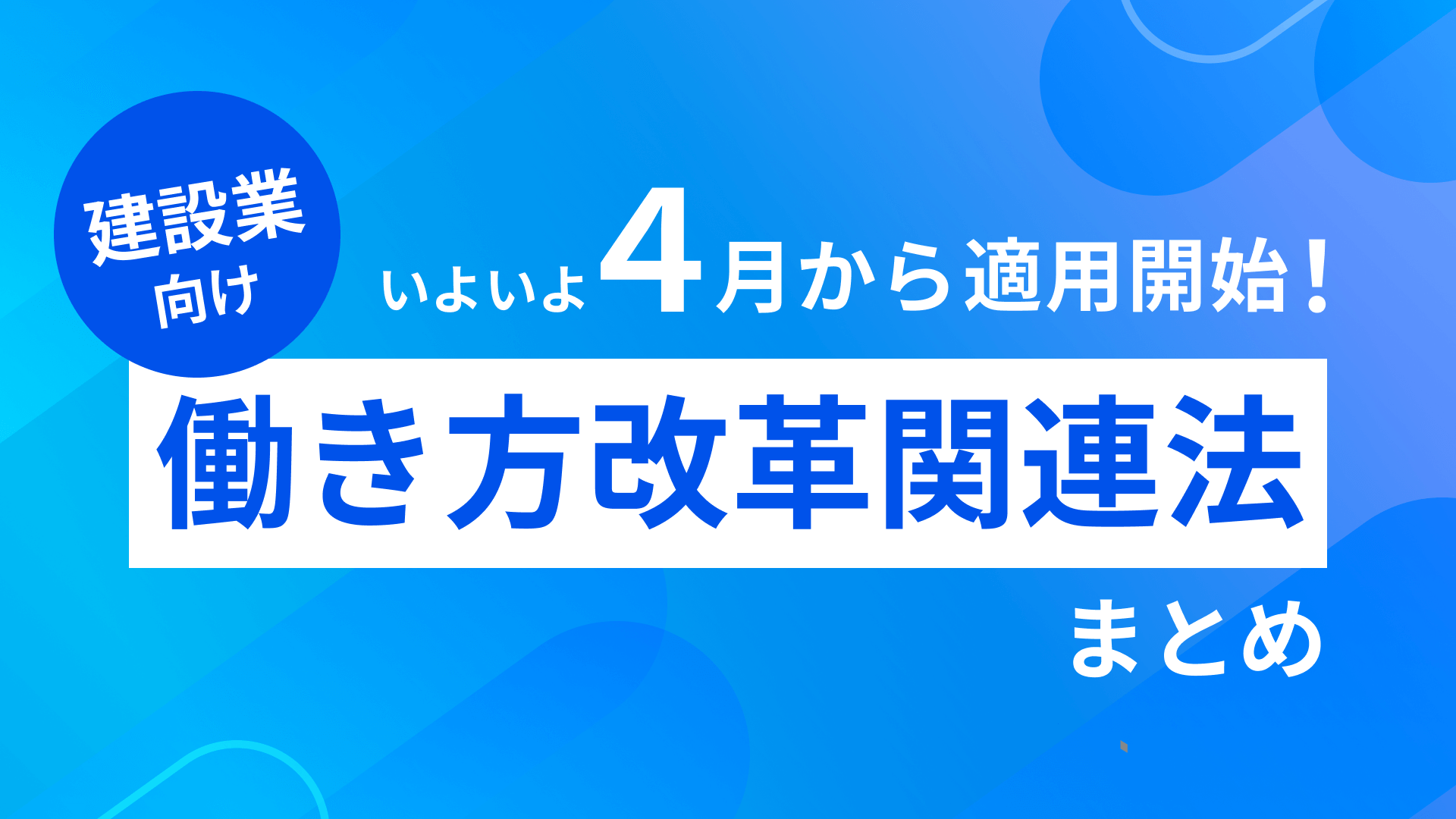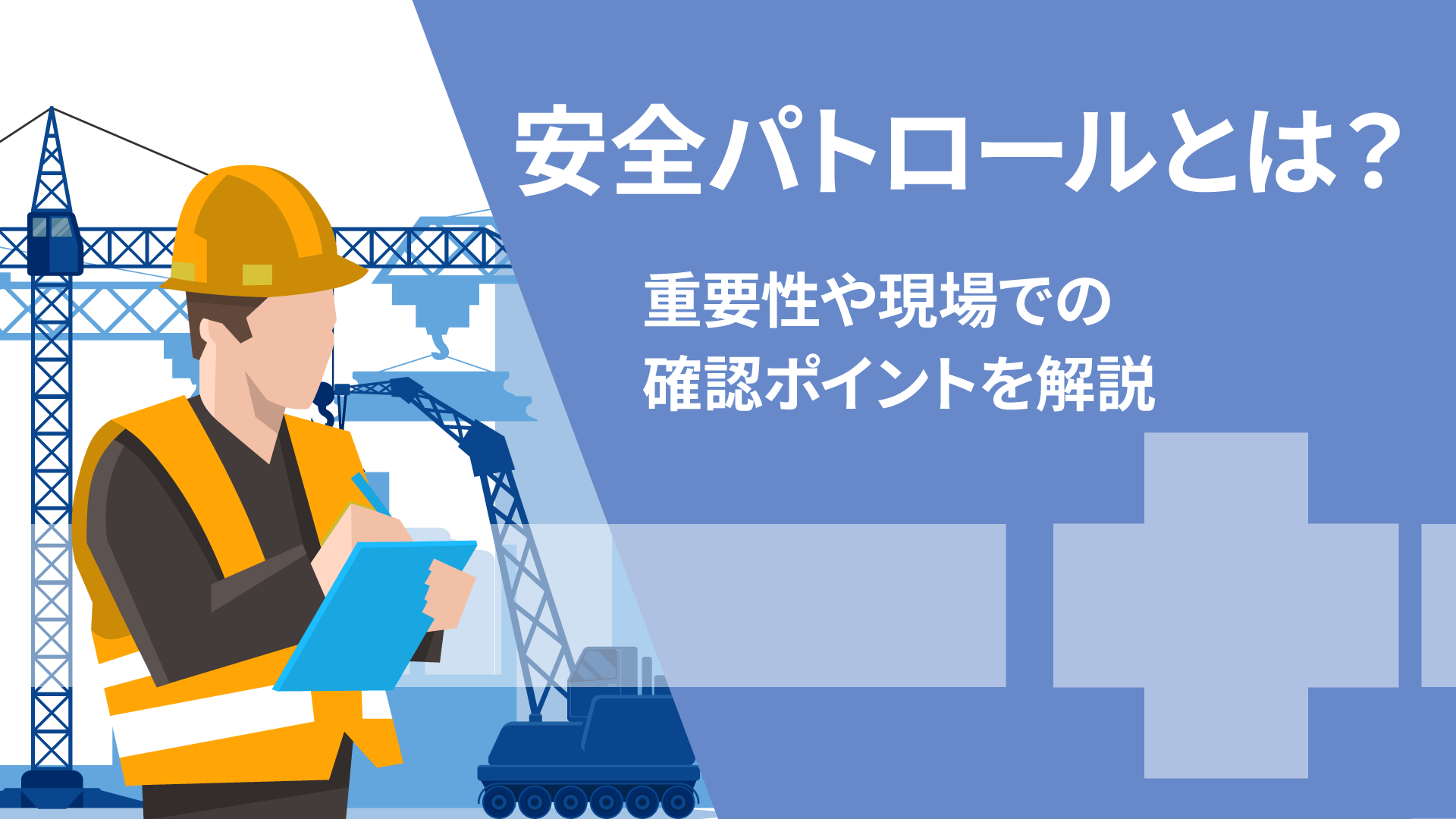建設業における残業の上限規制は?働き方改善のポイントも紹介
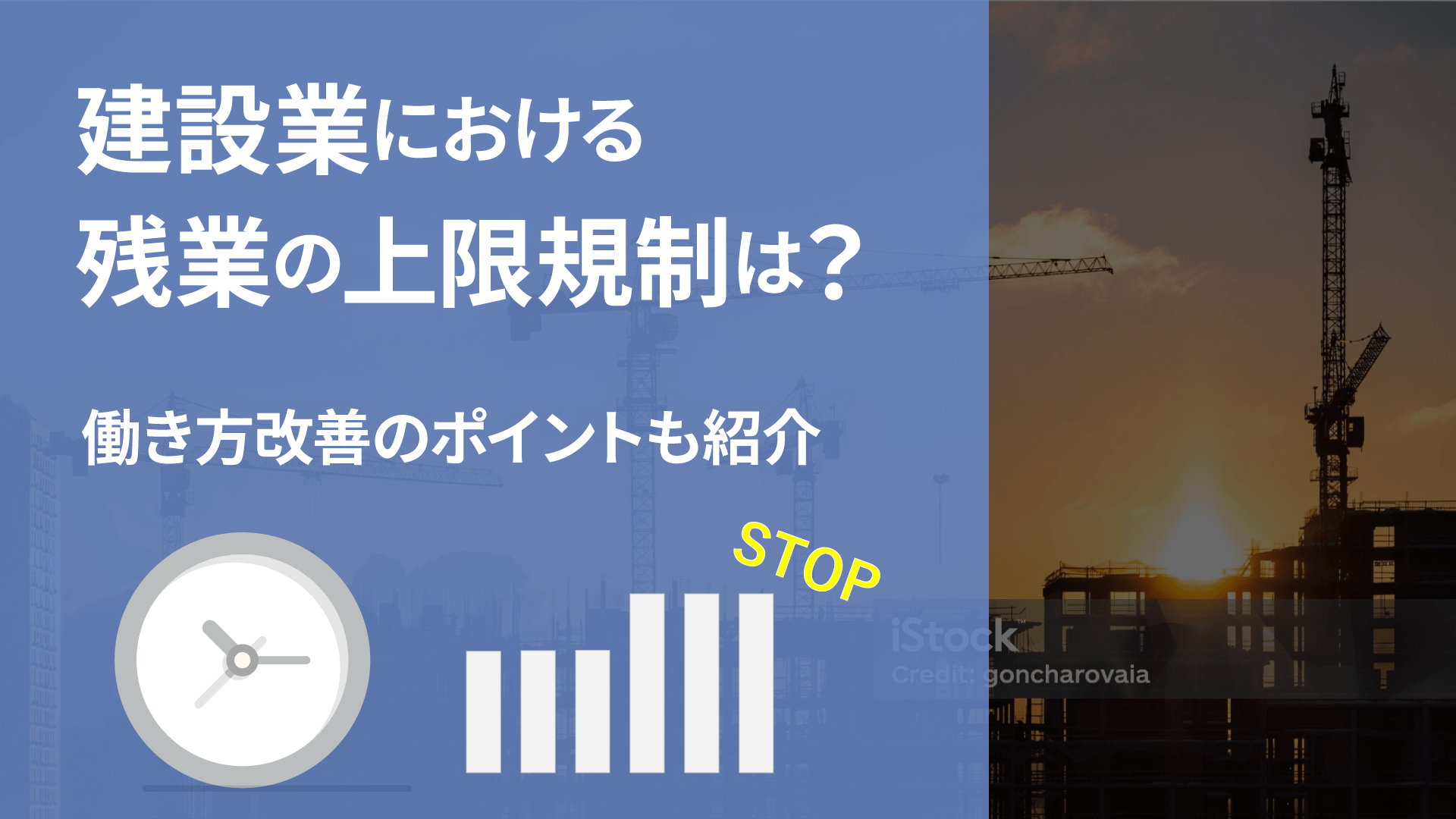
経過措置の終了により、2024年4月から建設業の残業規制が大きく変わりました。それに伴い、制度への理解や働き方の改善が求められています。
本記事では、2024年4月以降の建設業における残業規制、残業の課題、規制への対応ポイントについて解説します。
建設業での残業の上限規制はどうなる?
2024年4月以降から改正された36協定(サブロク協定)の適用により、残業の上限規制が変更となっています。適用前と適用後の労働時間規制に関する違いは以下のとおりです。
| 適応前 ~2024年3月31 |
改正後 2024年4月1日~ |
|
| 適用される36協定 | 改正前の36協定(経過措置) | 改正後の36協定 |
| 特別条項なしで延長可能 | 月45時間 / 年360時間(変形労働時間制を除く) | 月45時間 / 年360時間(変形労働時間制を除く) |
| 強制力・罰則の有無 | 強制力・罰則なし | 強制力罰則あり |
| 特別条項ありで延長可能 | ・年間6月まで ※強制力・罰則なし |
・年間6月まで ・年間720時間まで ・休日労働を含め、複数月平均80時間以内、単月100時間未満(災害時における復旧等の事業を除く) ※強制力・罰則あり |
以下から、2024年4月以降の建設業における残業時間の規制について解説します。
労働時間は「1日8時間・1週間で40時間」が原則
労働基準法では、事業者が労働者に働かせられる時間が1日あたり、1週間あたりで「法定労働時間」として定められています。法定労働時間は、1日8時間(休憩を除く)、1週間40時間です。これらを超えた場合は、法定時間外労働として扱われ、労働基準法違反となります。
労働者に法定労働時間を超えて労働させるためには、労使協定(36協定)の締結が必要です。36協定を締結することで、原則として月45時間・年間360時間まで法定労働時間を超えて労働させられます。なお、法定労働時間を超えた労働時間が発生した場合は、割増賃金の支払いが必要です。
2024年から建設業にも残業の上限規制が適用
36協定は、協定内に特別条項を加えることで、臨時的・特別な事情がある場合に限った時間外労働の上限を、上記規制を超えて設けられます。2019年の労働基準法改正以前は、この特別条項によって、年間6カ月まで、時間の制限なく労働させることができました。また、罰則が規定されていなかったため、事実上は労働時間の制限がない状態でした。
2019年の労働基準法改正以降の法定時間外労働は、特別条項があったとしても年間720時間まで、休日労働を含め複数月平均80時間以内、単月100時間未満、45時間を超える月は1年につき6カ月以内と制限されています。さらに、6カ月以下の懲役、30万円以下の罰金と、違反した場合の罰則が明文化されました。

改正当初は経過措置として、上記の上限規制は大企業への適用に限定されていました(2020年には中小企業に適用)。建設業をはじめとしたすぐに適用が難しい業務には、5年の適用猶予期間が設けられていました。2024年4月からは、建設業を含めすべての業種において上限規制が適用されています。
建設業における働き方の現状と規制の背景
36協定の上限規制適用以降、建設業はそれまで以上に時間外労働を抑制する必要に迫られています。しかし、建設業界にとっては以下のような課題があり決して簡単なことではありません。
- ▼他産業よりも長い労働時間・曖昧な休暇
工数を管理するうえで残業が増える傾向にあり、年間で90時間ほど長く、天候の影響も受けやすい - ▼人手不足と労働者の高齢化
慢性的な高齢化と人口減少に伴い、若年層の減少傾向が顕著 - ▼勤怠管理をするうえ多くの課題を抱えている
現場によって作業時間が異なり、手書きで管理している事が多く管理するうえで信頼性が低い
ここからは、建設業における働き方の現状、および規制の背景についてくわしく解説します。
他産業よりも長い労働時間・曖昧な休暇
建設業界は他産業よりも労働時間が長くなりやすい業界です。事業の最終期日が設定されているため、工数管理上で無理やり合わせる必要が生じ、残業せざるを得ない状況が多々存在します。実際に、建設業の残業時間は、他産業と比べ年間で90時間程度長いといわれています。
また、労働時間・休日の管理も曖昧になる傾向があります。これは、建設業が他業種に比べて天候の影響を受けやすかったり、移動に伴う待ち時間の発生で作業が鈍化したりすることなどが理由として挙げられます。結果として、残業せざるを得ない状況がつくられるのです。

人手不足と労働者の高齢化
建設業界では、人手不足と労働者の慢性的な高齢化が問題になっています。国内の人口減少が進んでいることに加え、働く若年層が減少傾向にある現代ですが、建設業は特にその傾向が顕著です。結果として、人手不足により一人当たりの作業量が増え、それが熟年労働者にとって過度な負担となり、労働時間の長期化に拍車がかかっています。
勤怠管理をするうえ多くの課題を抱えている
建設業界には、勤怠管理における課題が多く残されています。一般的に、現場ごとに作業開始・終了時間が異なるため、労働者に労働時間の管理を任せていると記録漏れや誤記入が頻発します。また、慣例的に手書きの記録を採用している現場が多いため、勤怠データの信頼性が低い点も問題です。
現場ごとに手書きで記入された労働時間をエクセルなどにまとめる際には、管理者に煩雑な作業を強いることになります。現場の進捗に合わせた勤怠データが即時確認できず、調整が遅れるケースも少なくありません。結果的に、集計の遅延で過重労働が事後的にしか発見されない事態が多発します。

建設業で残業規制に対応する3つのポイント
建設業における残業を減らし上限規制に対応するためには、新システムの導入や働き方の見直しが必要です。残業規制に対応するための代表的な3つのポイントを紹介します。
- ▼勤怠管理システムを導入する
出退勤を自動記録することで管理上での人的ミスを減らす - ▼柔軟な働き方を推進する
現場と事務の役割を分担し、労働負担を均等化することで不要な残業をなくす - ▼デジタル技術を用いた業務効率化
設計から施工までをデジタル化して共有、遠隔臨場を導入し移動時間などを短縮
それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。
勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムの導入は、一つの対応策です。労働者の、出退勤を自動記録するシステムを採用すれば、ヒューマンエラーによる出退勤時間の記録ミスが少なくなります。記録はデータへすぐ反映されるため、管理者は全従業員の勤務状況を即時に把握できます。
柔軟な働き方を推進する
労働時間を短縮するためには、建設業界の働き方を大きく変えることも求められます。労働負担を均等化するため、現場と事務の役割分担を徹底しましょう。無駄な残業や休日作業をなくす環境づくりを構築するのが重要です。
また、工事内容や天候に応じて作業開始時間を柔軟に設定することも重要です。遠隔で現場を管理できる環境があれば、現場に足を運ばなくてもできる作業の幅が広がるでしょう。SynQ Remote(シンクリモート)であれば遠隔臨場を簡単に行うことが可能です。
デジタル技術を用いた業務効率化
デジタル技術の活用で、効率的に業務を遂行できるようになります。BIM(Building Information Modeling)を導入し、設計から施工までの情報をデジタルで共有することで、工程ミスを削減可能です。ドローンによる計測・現場監視も、人手のリソースを削減する方法として挙げられます。

業務効率化についても、SynQ Remote(シンクリモート)を導入すると、遠隔臨場を遠方から実施でき、移動時間などの節約につながります。
遠隔臨場について詳しくは「▶遠隔臨場とは?注目されている背景や導入メリット、注意点を紹介」を御覧ください。
「SynQ Remote」ならスマホから現場調査・検査ができる!
建設業では、2024年4月以降、特別条項付きの36協定を結んでいたとしても、労働者を際限なく働かせることはできません。適法な労働時間に収めるためには、多くの現場で働き方の変化や、新システムの導入が求められるでしょう。
SynQ Remote(シンクリモート)は、遠隔での現場監視ができるシステムであり、すでに多くの建設現場で労働時間短縮の対応策として導入されています。残業時間規制の対応に苦慮しているのであれば、ぜひ導入をご検討ください。