遠隔臨場とは?注目されている背景や導入メリット、注意点を紹介
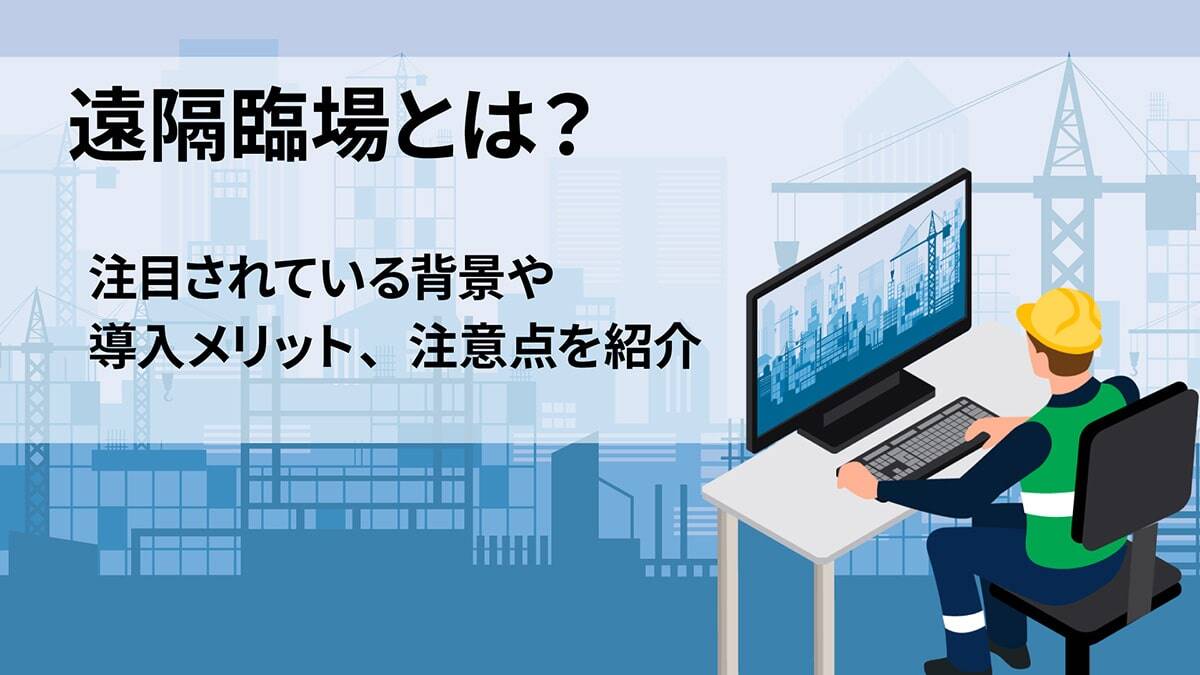
遠隔臨場では、現場の立ち会いを遠隔から実現する“遠隔臨場”に注目が集まっています。作業員の生産性を高めるためには、この遠隔臨場を理解し、適切に導入することが大切です。
本記事では、遠隔臨場がどういったものなのか、遠隔臨場の導入メリットや課題について解説します。
遠隔臨場とは?離れた場所から現場の立ち会いなどを行うこと
遠隔臨場とは、ウェアラブルカメラやネットワークカメラなどの遠隔臨場カメラによって、現場から離れた場所で臨場を行うことです。国土交通省の定義では、遠隔臨場を「材料確認」「段階確認」「立ち合い」を遠隔で行うこと、とされています。
このように、遠隔臨場を行う上で遠隔臨場用のカメラは重要です。
遠隔臨場カメラについては「▶遠隔臨場カメラとは?メリットや導入事例をわかりやすく解説」を御覧ください。

遠隔臨場が注目されている背景
遠隔臨場が注目される背景には、新型コロナウイルスの感染拡大の影響や国土交通省が取り組む建設現場の生産向上施策があります。特に生産性工場の施策については今でも重要な課題として注目を集めています。
働き方改革や国土交通省のi-Constructionの推進
国土交通省による「i-Construction」において、ICTの活用による建築現場の生産性向上は、プロジェクトの目的のひとつにも挙げられるポイントです。
労働人口の減少によって人材不足が加速している現在、多くの事業者にとって業務効率化は喫緊の課題です。そのため、ICT技術で業務改革を図ることで、働き方改革や生産性向上が求められています。
各地域は独自に「i-Construction」のルールを整備しています。例として、福岡県土整備部は段階確認、材料確認、立ち会いだけではなく、現場不一致、事故報告にまで、ウェアラブルカメラの活用を広げています。

遠隔臨場を行うメリット
遠隔臨場の導入することで主に5つのメリットが得られます。

以下では、遠隔臨場による代表的なメリットを紹介します。
移動等の時間削減や効率的な時間活用ができる
遠隔臨場を活用すると、現場までの往復の移動時間や複数現場の巡回にかかる時間を削減できます。作業員の労働時間削減に効果が見込まれ、新型コロナウイルス対策としても注目されました。削減された時間はほかの業務に充てられるため、効率的な時間運用が可能になります。
コスト削減できる
工事現場に必要な人員を減らせるため、人件費にかかるコスト削減に貢献します。1台の設備で、複数の人員に相当する業務を実施可能です。遠隔で実施することで、作業員の移動にかかるコストも削減ができます。
安全性が向上する
遠隔臨場は、現場の安全性向上につながります。遠隔地にいる専門家や管理者が現場に立ち会う機会を増やせるため、現場で起きているトラブルを早い段階で検知できます。現場に足を運ぶことなく、意思決定を迅速に行えるため、トラブルを未然に防ぎやすくなるでしょう。
人材育成につながる
遠隔臨場は人材育成の面でも役立ちます。ウェアラブルカメラを利用すれば、現場の熟練作業員の作業を若手に伝えることも可能です。熟練者の業務の様子や特殊な現場での作業内容を記録しておき、教材として残しておくこともできます。

人手不足が解消する
遠隔臨場による効率化は、人手不足の解消にもつながります。複数の現場を同時並行で管理できるため、各現場に人員を配置する必要はありません。重要な業務に人材のリソースを充てられます。
遠隔臨場の課題・注意点
遠隔臨場を導入する際は、それぞれの課題を認識したうえで、対応策を用意しておくことが大切です。遠隔臨場を導入する際の、主な注意点を紹介します。
事前準備のハードルが高い
遠隔臨場のデメリットとして、事前準備のハードルの高さが挙げられます。現場に適した機材の選定、機材の準備・設置、通信環境の整備など、事前準備が多くあります。また、機器導入のコストとして、ツールによってウェアラブルカメラなどのカメラ機器や録画機器が必要です。
「SynQ Remote(シンクリモート)」であればアプリを使わずQRコードを読み取るだけで遠隔臨場を行えるため、導入コストを削減できます。
IT機器に不慣れな人への対応
遠隔臨場システムは、一般的に操作が簡単な機器を用いますが、不慣れな作業員にとっては負担になることがあります。必要に応じて研修などを実施したりする必要があるでしょう。マニュアルを用意する際は、作成の作業が負担となります。
できるだけわかりやすいマニュアルを用意したり、操作サポートを充実させたりすることで負担が軽減するので、事前に現場の要望や意見などを丁寧にヒアリングしておくことが大切です。
通信環境の整備
通信環境整備の手間も、遠隔臨場のデメリットとして挙げられます。インターネットを利用する遠隔臨場システムは、環境によっては通信品質が低下します。特に、トンネル内などは電波が遮断され、音声が途切れる、映像が乱れるといったケースが少なくありません。
事前に通信状況をテストしたり、若手が作業する場合に熟練の技術者がカメラ越しにサポートする体制を整えたりすることで、こうしたデメリットを緩和できます。
現場臨場との違いがある
遠隔臨場には限界があり、現場臨場と同じように考えることはできません。例として、視野がカメラ目線のみに限られる、音声がよく聞こえない、細かい部分や数値は判別しづらいがある、といった点が挙げられます。普段使い慣れた機器で行うことで、操作などで生じる問題を改善できるでしょう。
遠隔臨場の取り組み成功事例
遠隔臨場はすでに多くの現場に導入されています。実際に遠隔臨場の取り組みに成功している事例を2つ紹介します。

宮崎県都城市:オンラインで確認し、移動時間や待ち時間を短縮
宮崎県都城市では、市の面積が広く、公共工事の現場確認の移動に往復1時間かかることが問題になっていました。また、土質試験の立ち会いのため1日に何度か現場に行く必要があり、その点も受注業者に負担を強いていました。
解決のため、自治体は受注業者に対して遠隔臨場・シンクリモートを導入したころ、材料確認をオンラインでチェックできるようになり、移動時間が削減されました。
また、現場に行かずに土質試験を実施できるようになり、証跡も遠隔撮影で記録できるようになりました。他にも、受注業者のストレスの軽減や、待ち時間削減にも貢献しています。
宮崎県都城市の遠隔臨場・シンクリモートの導入事例については「▶公共工事で自治体が受注業者にアカウント配布して活用。広域な都城市で往復1時間の移動を削減」を御覧ください。
神奈川県建設業:県をまたぐ複数の現場管理で移動コストを大幅削減
神奈川県のある建設事業者は県をまたいで複数の現場を抱えており、現場間の移動に時間がかかっていました。現場から送られてくる写真では状況がわかりづらいことも問題になっていました。ビデオ通話でも、現場の状況を正確に把握することは困難でした。
遠隔臨場・シンクリモートを導入してからは、ポインタによる詳細な細かい指示ができるため、多くの場合、現場に行かずに対応が完了します。問題が発生したときや、確認したいときにすぐに元を確認できるため、作業がスムーズに進められ工数に遅れが出にくくなりました。
神奈川県建設業の遠隔臨場・シンクリモートの導入事例については「▶県をまたぐ複数の現場管理に。現場の把握だけではなく、的確な「指示」が出せるポインタ機能で移動コストを大幅削減。」を御覧ください。
遠隔臨場に役立つすぐに誰とでも繋がれる「SynQ Remote(シンクリモート)」
建築現場で慢性的になっている問題の多くは遠隔臨場で解決します。一方で、遠隔臨場の導入には、設備の準備などいくつかの課題が存在することも事実です。複数の法人が絡む建築業では、同一のシステムを導入することが困難な場合もあります。
法人をまたいで、関係者全員が共通システムを導入することは、セキュリティ上の問題により容易ではありません。その点、現場仕事に特化した遠隔支援ツール「SynQ Remote(シンクリモート)」はユーザー登録なしでPCやアプリから誰でも参加可能で、複数の法人が参加する現場でも簡単に導入できます。 建築業で遠隔臨場を導入したい場合は、ぜひご検討ください。



